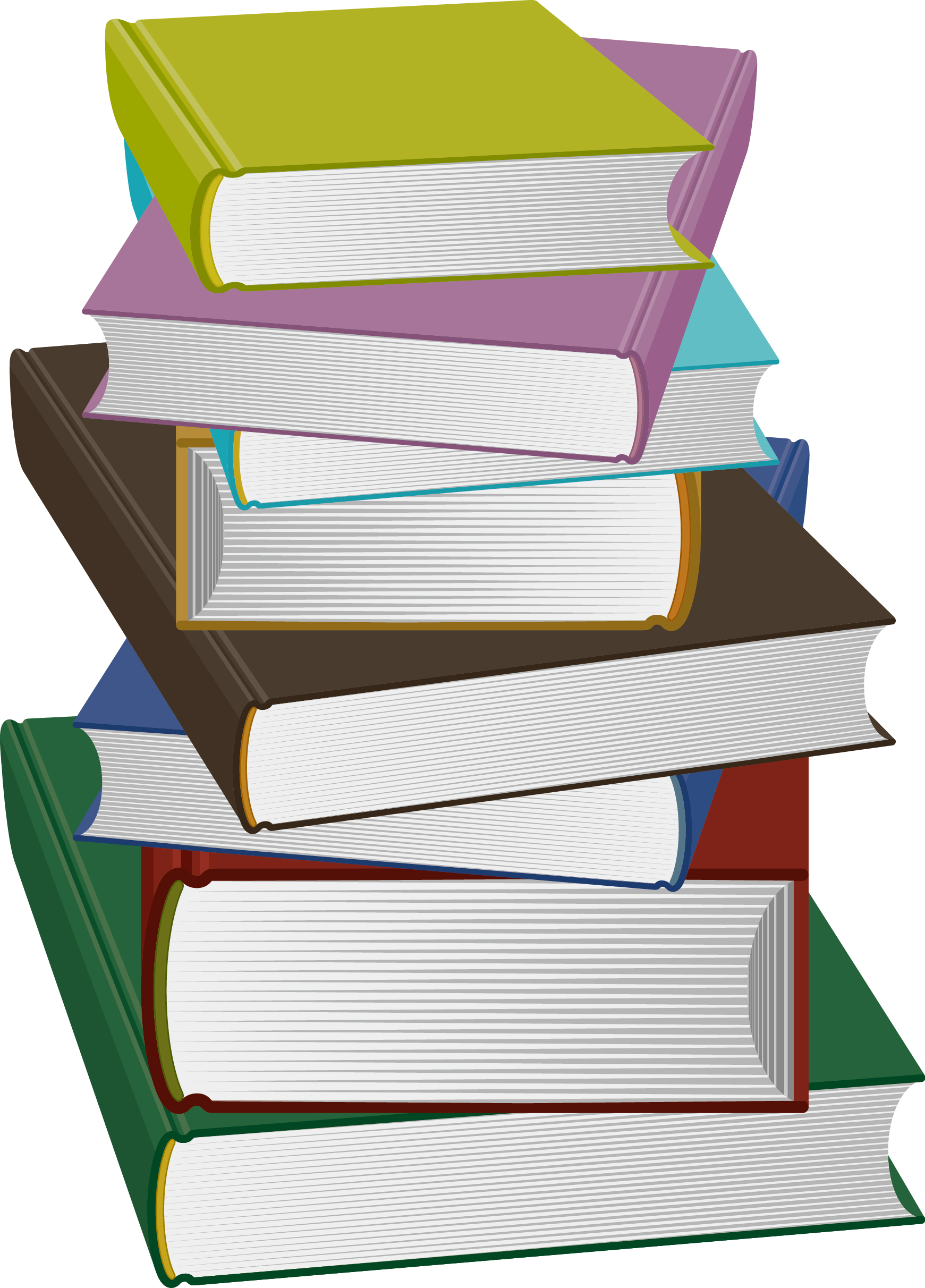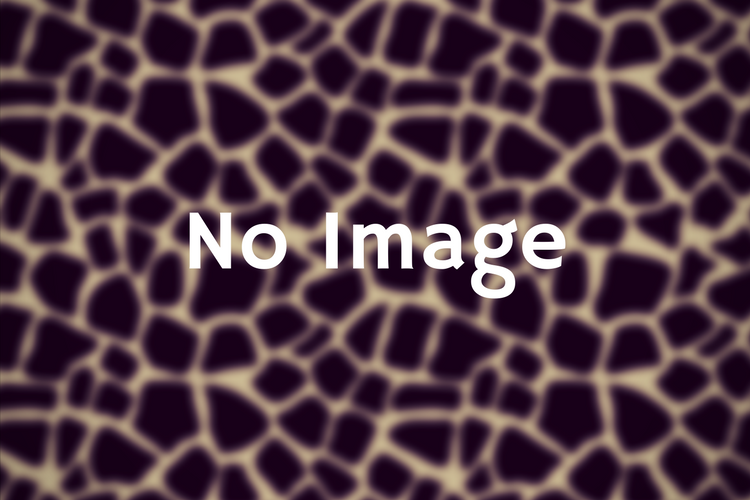【宅建受験者必見】2025年法改正で変わる宅建業法 ― 「過去問の正解」が不正解になる!?その理由と意義を徹底解説!
こんにちは。
2025年4月1日より、宅建業法を中心に関係法令が改正されました。これにより、昨年度までの宅建試験において「正解」とされていた過去問の一部が、「不正解」になる可能性があるという事態が起こっています。
この記事では、「一体どこが変わったのか?」「なぜ変えられたのか?」「それによってどう対応すればいいのか?」を受験者目線でわかりやすく解説していきます。
目次
法改正によって変わった主要ポイントはこの6つ!
① 国土交通大臣免許の申請手続きがシンプルに!
【改正前】 複数の都道府県に事務所を持つ業者が免許を申請する際は、都道府県知事を「経由」して国土交通大臣に申請する必要がありました。
【改正後】 都道府県知事の経由が不要に。主たる事務所の所在地を管轄する「国土交通省地方整備局」に直接申請できるようになりました。
【なぜ改正?】 行政手続のデジタル化が進むなか、「経由」という回り道をなくし、手続きを効率化するためです。
【出題例との関係】 令和5年問28では「知事を経由して提出する」が正解でしたが、今後は「直接提出する」が正解になります。
② 宅建業者名簿・従業者名簿の記載ルールが変更
【改正前】
-
宅建業者名簿には専任の宅建士の「氏名」を記載。
-
従業者名簿には「性別・生年月日」の記載が必要。
【改正後】
-
宅建士の「氏名」は不要。
-
性別・生年月日の記載も不要に。
【なぜ改正?】 個人情報保護の観点から、必要性が低くリスクの高い情報は記載しない方向へ。
【出題例との関係】 令和4年問30のように「氏名の記載が必要」とあったものは、今後誤りとなります。
③ 標識に記載する内容も見直し
【改正前】 標識には専任の宅建士の「氏名」を記載。
【改正後】 氏名ではなく、人数と事務所の代表者の氏名を記載。
【なぜ改正?】 これもプライバシー保護のため。標識は一般の目に触れる場所に掲示されるため、宅建士個人を特定する必要はないと判断されました。
【出題例との関係】 令和3年問32では「氏名の記載」が正解でしたが、今後は誤りとなる選択肢に。
④ レインズ登録事項の追加:「申込みの受付状況」
【改正前】 レインズに登録する情報には、「取引申込みの状況」は含まれていませんでした。
【改正後】 「申込み受付の有無」を登録する義務が追加されました。
【なぜ改正?】 レインズ情報の鮮度を上げることで、「もう申込が入ってるのに未登録」というトラブルを防ぐ狙いです。
【出題例との関係】 令和2年問34などで「申込み状況は登録事項ではない」とされていた内容が、今後は誤りになります。
⑤ 空き家等の売買にかかる報酬上限額が増額!
【改正前】 売買価格400万円以下の空き家に限り、18万円(税抜)までの手数料が認められていました。
【改正後】 対象物件の価格が800万円以下に引き上げられ、報酬額は最大30万円(税抜)までOKに。
【なぜ改正?】 地方の空き家流通を活性化するため。価格が安くても業者の手間は同じなので、適切な報酬を確保できるようにした。
【出題例との関係】 令和元年問36などで「400万円以下」がキーワードだった問題は、今後は「800万円以下」が正解ラインに。
⑥ 建築確認申請の義務が拡大!
【改正前】 都市計画区域外では、木造で200㎡以下・2階建て以内であれば建築確認が不要。
【改正後】 200㎡超の木造建築や、2階建てでも広さがある建築物には、都市計画区域外でも確認申請が必要に。
【なぜ改正?】 近年の自然災害の多発を踏まえ、地域に関係なく最低限の安全基準を担保するためです。
【出題例との関係】 令和2年問15などで「都市計画区域外は不要」とされていた内容が、一定条件下では誤りになります。
法改正をどう勉強に活かすか?
■ 過去問に依存しすぎない!
過去問演習は宅建試験対策の王道ですが、「正答の根拠が古い法令によるもの」であれば、今では正解とは限りません。特に上記のような改正点が含まれる分野では注意が必要です。
■ 最新の法改正を押さえよう!
市販のテキストや問題集を使う場合でも、2025年対応版であることを確認してください。また、LECやTACなど大手予備校の模試や直前対策講座では、改正点に基づいた問題が出されることが多いため、有効活用をおすすめします。
まとめ
今回の2025年法改正は、単なる数字や手続の変更ではなく、現代の不動産流通における「情報の精度」「個人情報保護」「行政手続の簡素化」といった時代の流れを色濃く反映しています。
受験生としては、「なぜ改正されたか」を理解しておくことで、選択肢に迷ったときの判断材料になりますし、実務家を目指す視点としても大きな意味があります。
今年の宅建試験で「これ、去年までは正解だったのに…」という失点をしないためにも、ぜひこのブログ記事を何度も読み返して、改正内容を自分の中に定着させてください。